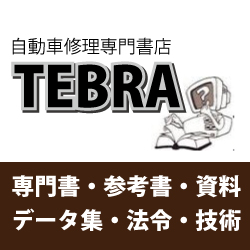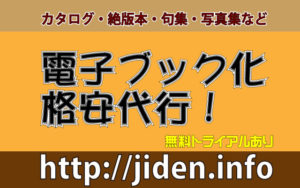●夏の大敵 食中毒
暑い夏、この時期私たちがもっとも気をつけなくてはならないのが「食中毒」です。食中毒は季節に関係なく発生しますが、特に夏の暑さと湿気で細菌が増えやすく、多くの人が苦しみ、中にはなくなる方もいます。
戦前から戦後の1960年代くらいまで、毎年300人ほどの人が食中毒で亡くなってしまっていたのです。それが60年代から年々食中毒患者は激減して、現代では年に数人まで減りました。
減った原因はいくつかありますが、衛生管理が発達したのと、冷蔵庫・冷凍庫の普及による食の保存にあります。私たちはこのテクノロジーにもっと感謝すべきでしょう。
●冷凍庫がない時代でも支配者は氷菓子を食べていた
いま私たちが普通にお刺身を食べることができるのは、魚の冷凍技術の発達や冷蔵庫で保存ができるようになったからです。
特に夏のお刺身は、漁村などの地域や、魚市場のすぐ近くでないと食べることはできませんでした。魚がたちまち傷んでしまうからです。
そのことを思うと、現代社会に生きる私たちは、真夏に冷たいお刺身、氷を使って冷たい飲み物や氷菓子を食べられるというのは、とてつもなく贅沢と言えるでしょう。
もっとも冷蔵庫・冷凍庫のない時代でも、王侯貴族は夏に冷たい食べ物を楽しんでいました。
いまから2500年前の孔子が生きていた時代、中国には氷の貯蔵庫である巨大な氷室(ひむろ)があったことがわかっています。
古代ギリシャや古代ローマでも山から運んだかき氷にハチミツなどをかけて楽しんでいました。
日本でも清少納言の『枕草子』に「削り氷(けずりひ)」というかき氷が出てきます。山の洞窟などに「氷室(ひむろ)」to
いう氷の貯蔵施設を作り、夏になると氷を切り出して上級貴族や将軍などが涼を楽しんでいたようです。
●明治時代、ボストンから氷を輸入
とはいえ、夏に氷を楽しめるのはほんの一部の富裕層だけ。富士山の洞窟に氷室を作って江戸に運ぶとしても、その多くが溶けてしまいます。当然、氷の値は上がり庶民に手が届くわけもありません。
やがて時代は幕末をむかえ、これまで以上に海外との交流がはじまります。するとあるアメリカ人が、アメリカの東海岸にあるボストンから船で氷を輸入しはじめます。
当時はまだ西海岸から直接日本に行く航路はありません。ボストンから西アフリカに行き、南アフリカの喜望峰をぐる~とまわって、インド洋を航海してと、当時、米国から日本まで3~5か月かかりました。
●牛乳・牛肉、そして氷を広めた男
当然、日本につく頃にはかなりの氷が溶けていました。当然お値段は超高価。それを知った横浜で初代英国公使のオールコックのもとでコック見習いをしていた中川嘉兵衛さん。中川嘉兵衛さんは当時すでに40代でしたが、ヘボン式ローマ字で有名なヘボン博士から、食品の保存に氷が有効と教えられ、製氷業を思いつきます。 中川嘉兵衛さんは、その前に牛肉や牛乳の販売店を開業したりしていましたから、文明開化のこの時代、牛乳・牛肉が将来の日本で必要だという先見の明があったのでしょう。
当時の40代はいまの60代と同じようなものですから、相当柔軟な頭脳の持ち主だったのでしょうね。
最初は富士山など本州の寒冷地に氷室を作って横浜に運んでいましたが、やがて北海道の函館・五稜郭から氷を運んで大成功したといいます。
やがて、氷は天然氷から工場で製氷する機械氷が中心となり、戦後電気冷蔵庫の普及により、一般家庭でも氷を作ることができるようになりました。
●夏に庶民が氷を楽しめる時代が来た
冷蔵庫・冷凍庫の普及は、我々の食文化に大きな影響を与えました。我々は夏の暑い日にかき氷やアイスクリームを食べるなど、一部の王侯貴族しかできなかったことが、庶民が普通に楽しめるようになりました。
冷蔵・冷凍技術のおかげで、地球の裏側のお肉やお魚、野菜なども私たちの口に入るようになりました。 冷蔵・冷凍技術は世界中の食文化をガラリと変えました。食文化は人類の科学や進歩と密接に関係しているのです。
(巨椋修(おぐらおさむ):食文化研究家)24-08