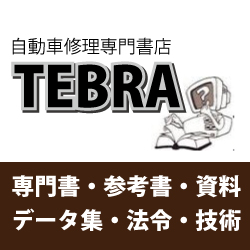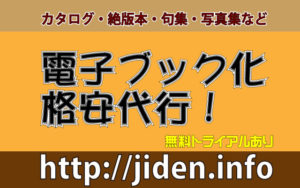トロイ遺跡を発掘したことで知られるシュリーマンは幕末に来日した際、「日本でもっとも大きくて有名な寺の本堂に花魁の肖像画が飾られている事実」を指摘。「他国では、人々は娼婦を憐れみ容認してはいるが、その身分は卑しく恥ずかしいものとされているが、日本人は、彼女らを、崇めさえしている」と記した。なるほど、彼の言うことは一面の真実だろう。が、彼は所詮、旅行者。「苦界」の実態を正確に記し得ていない。
まず、江戸において、幕府公認の遊廓は吉原だけだが、吉原は値段は高いし、煩わしい仕来りも多い。結果、庶民の足は非公認の私娼街である岡場所へと流れたが、岡場所の繁盛は吉原には歓迎できる事態では無いから、吉原は幕府へ岡場所の取締りを要請。摘発された遊女たちは縛られた上に髪に値札をつけられ、次の「飼い主」が決まるまで道端で待機させられた。(この光景は、さすがに同時代人の目にも異様に映ったという。)彼女たちが吉原の各遊郭へと払い下げられていったことから、吉原では一種の在庫過剰現象が起きる。結果、その待遇は売春以前に、食事も満足に与えられないほどに劣悪極まりないものとなった。
さらに、岡場所にしろ、吉原にしろ、仕切っている連中は必ずしも褒められた輩では無い。「年季は最長十年」と呼ばれたが、実際には、借金は簡単には減らない仕掛けになっており、つまり、自由の身となるためには、金持ちの客に「身請け」されるか、「死ぬ」かの二つしか無かったのである。(後者の例で言えば、中絶の失敗から、梅毒などの性病、劣悪な環境による結核やチフスに果ては心中なども珍しいことではなかったが、前者の例も、容姿に自信があるほんの一握りだけで、決して多くはなかっただろう。)
では、身請けもされず、死ぬこともならず、時間だけが経って、「商品」としての価値が落ちた者はどうなるか?選択肢としてあるのは、「商品」としての「値段」を下げることだけである。彼女たちは、梅毒で鼻が取れるなど、不自由な身体になりながらも、なおも、厚塗りしたお白粉で皺を隠し、筵を一枚抱え、川縁や辻々に立ったが、そのような状態では、もはや、値段はあってないようなもの。俳人・小林一茶は、「木がらしや二十四文の遊女小屋」と詠んで、夜なきそば一杯の値段より少し高いだけの額で自らを売る女たちを憐れんでいる。
では、これら以外の一般の女性は普通の生活が営めたかと言うと、これも、そう単純な話でもない。生活苦というものが背景にある以上、背に腹は代えられぬで、家に居ながらにして口コミで客を取るようになるのである。江戸は現代人が考えるほど優しい世界ではない。
(小説家 池田平太郎)2025-03