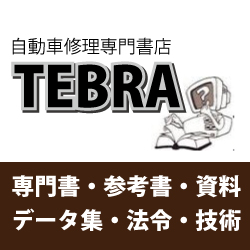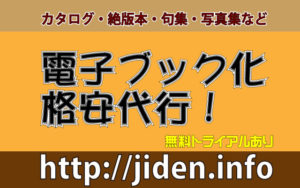私たちの食卓は、時代とともにずいぶん姿を変えてきました。戦後の混乱期を乗り越え、経済の成長とともに豊かになった日本の「食」。今回は1950年代から2020年代までを10年刻みでふり返りながら、日本の食文化の変化を見ていきたいと思います。
◆ 1950年代:給食とパンの普及
戦後まもないこの時代は、まだ食糧事情が厳しく、十分に食べられない家庭も多くありました。そんな中、子どもたちの命綱となったのが、GHQの援助で始まった学校給食です。コッペパンに脱脂粉乳というメニューが多くの子どもたちの栄養不良から救いました。
また、これまでお菓子だったパンが、主食の一つになりつつあった時代でもありました。現在、もっともパンが好きな年代は、この時代に給食でパンを食べていた70代前後の人たちだそうです。
◆ 1960年代:インスタント食品と家電革命
高度経済成長が始まり、人々の暮らしが豊かになってきた1960年代。冷蔵庫や炊飯器といった電化製品が家庭に普及し、料理がぐっとラクになりました。
この時代にヒットした「インスタントラーメン」は、まさに食の革命でした。他にも、60年代後半にはインスタント味噌汁やレトルトカレーが登場。インスタントコーヒーや缶詰も家庭に入ってきました。
◆ 1970年代:ファミレスとハンバーガーの登場
1970年の大阪万博をきっかけに、日本の食もグローバル化の波に乗り始めます。1971年には日本初のマクドナルドがオープン。すかいらーくに代表されるファミリーレストランもこの時期に登場し、「外食」が特別なものから日常の選択肢になっていきました。
カレーやスパゲティといった「洋食」も当たり前になり、食卓は一気にカラフルに。「何を食べようか」の選択肢がぐんと広がった時代です。
◆ 1980年代:グルメブームとバブルの香り
バブル経済の時代であった1980年代では、「グルメブーム」が起こります。「美味しいものを知っているのがカッコいい」という空気がありました。
テレビや雑誌でも食特集が組まれ、有名シェフや話題のレストランが注目を集める一方、コンビニ弁当やコンビニおにぎりも進化した時代です。
◆ 1990年代:安くてうまい、B級グルメの時代
バブルがはじけ、不況が訪れた90年代は、「高級」より「実用」へとシフトします。牛丼チェーンや回転寿司といった、「安くておいしい」外食が人気を集めました。
この頃から「B級グルメ」という言葉も生まれ、地域の名物料理や庶民の味が注目されるように。家庭では共働きや一人暮らしの増加を背景に、冷凍食品やレトルト食品のバリエーションも増えていきました。
◆ 2000年代:安全・安心・健康ブーム
2000年代に入ると、食の安全に対する意識が高まります。牛肉の狂牛病問題や食品偽装事件などが相次いだのです。
朝食を抜く子どもが増え、食の乱れから肥満や成人病の増加に対応するため、「食育基本法」が制定されます。一方で、糖質制限やカロリーコントロールといった「健康志向の食事」も人気に。外食チェーンでもヘルシーメニューが登場し始めました。
◆ 2010年代:SNS映えと時短・個食の時代
スマートフォンとSNSの普及で、「見た目がかわいい」「写真を撮りたくなる」食べ物がブームに。いわゆる「映えるグルメ」が、日々SNSに投稿されました。
また、共働きや一人暮らしの増加を背景に、個食・時短志向が加速。コンビニのミールキットやレトルト総菜が進化し、「料理はしないけど、ちゃんと食べたい」ニーズに応えています。
◆ 2020年代:コロナ禍と食の変化
そして現在、2020年代。新型コロナウイルスの流行により、私たちの食生活は大きく変わりました。外食が制限され、テイクアウトやデリバリー、家での料理が見直されるように。
一方で、「地球にやさしい食」への関心も高まり、フードロス削減やプラントベース(代替肉)への注目が集まっています。
こうしてふり返ってみると、私たちの食卓は常に時代の空気とともに変化してきたことが分かります。技術の進化、社会の変化、そして世界とのつながり。それらすべてが、今の「いただきます」に繋がっているのです。未来の食卓も、きっとまた新しい「美味しさ」で彩られていくに違いありません。楽しみですね。
(巨椋修(おぐらおさむ):食文化研究所)2025-07