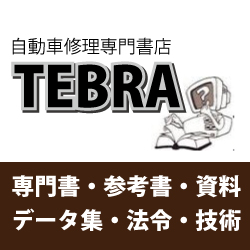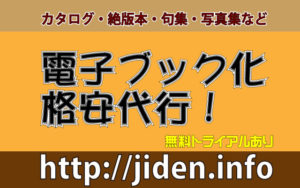一日の終わりに訪れる“安らぎ”の時間を、じっとりとした暑さが奪い去る熱帯夜。気象用語では夜間の気温が25度を下回らない夜の事。
かつては年に数えるほどだった熱帯夜も、今や珍しい存在ではない。扇風機の風がぬるく、窓から入る風が温風と化し、寝返りを打つたびにシーツが肌にまとわりつく。
扇風機の首振りに合わせて、壁の影がゆっくりと動く。夜が更けるほどに静寂は濃くなり、熱は逆にじんわりと体にまとわりついてくる。時計の針が一秒ずつ進む音がやけに大きく感じられるのは、きっと眠れぬ夜のせいだろう。 寝苦しいはずなのに、なぜかその感覚に懐かしさを覚えるのは、幼い頃の“夏の夜の記憶”が心のどこかに残っているからかもしれない。
現代の生活は、暑さを「しのぐ」ことばかりに注力するが、かつて人々は暑さと「共にある」ことに長けていたように思う。すだれに打ち水、氷柱や金魚、夜風に紛れて漂う焼きとうもろこしの匂い、近所の犬の短い鳴き声、そして誰かが水撒きをしているホースの音。虫の声が響く路地裏、夕涼みと称してベランダに出るひととき、冷やしたスイカや麦茶がなぜか特別に美味しい。子どものころ、蚊帳の中で聞いた虫の声や団扇であおがれながら聞いた祖母の昔話がふと蘇る。風鈴の音が遠くで揺れる。窓の外、同じように眠れずにいる誰かの気配を感じてしまうのも、熱帯夜の魔法のひとつだ。
熱帯夜には、そんな記憶の扉を開く力もある。――すべてが熱帯夜を彩る知恵であり、風情であった。すべてが静けさの中に溶け込み、やがて心をどこか穏やかにする。
そう考えると、熱帯夜とは単なる気象現象ではなく、日本人の暮らしと感性を映す鏡なのかもしれない。暑さを不快と切り捨てるのではなく、その中にある「静けさ」や「記憶」と向き合うこと。それこそが、熱帯夜を味わう唯一の方法なのだろう。
エアコンのリモコンに手を伸ばす前に、一度だけ、外の空気を吸ってみる。濃い夜の匂いと、少し湿った風に包まれながら、「ああ、夏が来ている」としみじみ思う。
現代の都市は熱を逃がす余白を持たない。コンクリートに蓄えられた昼の熱が、夜になっても街を離れず、空調に頼る暮らしがますます当たり前になる。だが、それでもベランダに出て夜空を見上げれば、月の光と虫の声に包まれて、夏を楽しむことが出来る。熱帯夜は、不快で、愛おしい。そんな矛盾を抱えた時間である。その瞬間こそが、熱帯夜の真の贈り物なのかもしれない。
(ジャーナリスト 井上勝彦)
(ジャーナリスト 井上勝彦)2025-07