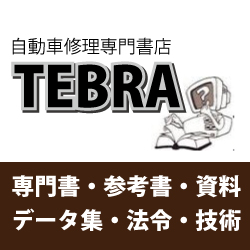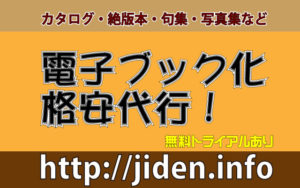●肉じゃがは東郷平八郎がビーフシチューを所望して……
日本帝国海軍が広めた料理として有名なのがカレーライスですが、他にももう一つあります。それが『肉じゃが』。
肉じゃが発祥説にはいくつかあるのですが、有名なのが日本海軍のリーダーのひとりであり、日清日露の戦争で大活躍をした東郷平八郎が、当時舞鶴鎮守府の初代長官だったとき、艦上でイギリスに留学していたころ食べたビーフシチューを食べたいと、コックにいったところ、残念ながら材料がなく、またコックにビーフシチューの知識がなかったため、あり合わせの材料でビーフシチューをイメージしたものを作ったのがはじまりという説があります。
しかしこの時代には限りなくビーフシチューに近いハヤシライスは誕生しており、すでに日本海軍の調理法を紹介した「五等厨夫教育規則」の中にシチューの作り方が記載されていることから、コックに知識がなかったかどうかは疑わしいところ。
先ほど海軍が広めた料理にカレーライスがあると述べましたが、この肉じゃがの材料とカレーの材料って、お肉、じゃがいも、ニンジン、タマネギなどかなりの部分で共通するんです。このカレーの材料をひと工夫してできたのが肉じゃがだったのかも知れません。
●肉じゃが誕生の地に二つの町があるけど……
「我が町こそ肉じゃが誕生の地である」と名乗りを挙げている場所が、2つあります。ひとつは東郷平八郎がいた京都府の舞鶴。もう一つは広島県の呉。どちらも海軍の基地があったところですが、さてどちらが肉じゃが誕生の地であるかというのは、わかっておらず確たる証拠もないのです。
わかっているのは、どうやら海軍が関係しているらしいということだけ。舞鶴と呉の共通点として海軍があったこと。両方に東郷平八郎が勤務していたことがありますが、東郷平八郎が勤務していたのは、呉が明治23年、舞鶴は明治34年と呉の方が早いのですが、だからといって東郷平八郎が肉じゃがと関係しているのかどうかは不明。
海軍料理研究家の高森直史氏の著書『帝国海軍料理物語』(光人社)によると、1988年にテレビ局から「肉じゃがは海軍にルーツがあった」「その場所は舞鶴だった」という結論ありきの企画があり、いろいろ調べたところ「海軍厨業管理教科書」に肉じゃがのルーツと思われる「甘煮」のレシピが載っており、「肉じゃがのルーツは海軍にあることが、舞鶴の資料でわかった」と答え放送されたといいます。
ここでは「舞鶴の資料でわかった」と言っており「舞鶴がルーツだった」とも「東郷平八郎が」とも言っていないのです。ところが、1995年、舞鶴側が町おこしのために「東郷平八郎が艦上でビーフシチューをコックに所望したところ……」という話を創作したといいます。
やがてこの話が有名になってくると、1997年「呉の方が先に東郷が赴任しているのだから」と「呉が発祥」と主張。目的はおなじく町おこしでした。この両者はいがみあっているわけではなく、町おこしのため肉じゃがを通して仲良くケンカをしているようです。
●肉じゃがは海軍兵の命を救っていた
肉じゃが発祥の地は不明ですが、肉じゃがという料理は実際に多くの海軍兵の命を救ったと思われます。というのも、当時、日本人の国民病として脚気(かっけ)がありました。
脚気はビタミンB1が欠乏して起こる病気。明治時代の日本軍は「白いメシが腹いっぱい食える」を売りにして兵隊を集めていました。
玄米にはビタミンB1が多く含まれていますが、白米にはほとんど入っていません。軍隊に入って白米ばかりを食べる兵隊さんは、当然脚気患者が激増します。ちなみに肉じゃがに入っている豚肉やジャガイモにはビタミンB1が入っていますので脚気予防になるわけです。
脚気の原因は食べ物にあるらしいと気がついた海軍は、パン食や洋食を取り入れることで、脚気患者の激減に成功しています。
陸軍は白米中心食を改めることができず、動員兵100万人のうち25万人が脚気に罹患し、戦病死者4万7千人のうち2万8千人が脚気で死亡してしまいました。
海軍では脚気は継承者のみで脚気による死亡者の報告はありません。肉じゃがなどの食事が海軍兵を脚気から守ったのです。
医食同源といいますが、現代に生きる我々も食事に注意したいですね。
(巨椋修(おぐらおさむ):食文化研究家)2025-01