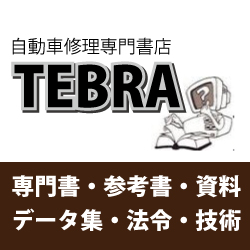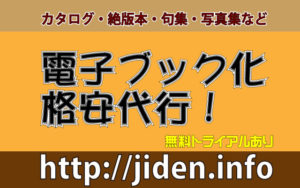●電子レンジは食文化の革命
電子レンジが本格的に家庭に普及し始めたのは、ざっくり1980年代あたり。それまでの食事といえば、「火を使う」が大前提だったのに、電子レンジの登場で「チンするだけ」という魔法のような調理が可能になりました。もうこれは、食文化の革命と言っても過言ではありません。
電子レンジの最大の功績は、何といっても料理時間の短縮です。例えば、ご飯を炊くにはガスや電気なら30分以上かかるのに、冷凍やパックに入っているご飯なら数分間チンするだけでホカホカ。カレーだって、鍋で温めるよりパウチごとチンする方が楽チン。
この「チンするだけ」の文化は、特に一人暮らしの人や忙しい共働き世帯にとってありがたいもので、お弁当を温めるのはもちろん、市販の冷凍食品が一気に進化し、「焼きたてのピザが3分で!」とか「揚げたての唐揚げが5分で!」なんて、電子レンジが普及する前では、ありえないことが現実になったのです。
●コンビニの進化と電子レンジ
コンビニ食品の進化も、電子レンジなしには語れません。1980年代末から1990年代にかけて、コンビニでは次々と「電子レンジ対応」の食品が登場しました。おにぎり、弁当、パスタ、スープ……コンビニの中にあるレンジでチンすれば、出来たてのような温かいご飯が食べられるようになりました。
特に、日本のコンビニは「レンジ対応食品」に本気を出し、レンジで温めるとモチモチ食感になるパスタや、皮がパリッとする唐揚げまで登場。これらの開発により、「コンビニ=冷たい食事」というイメージは完全に覆されることになります。
いまでは当たり前になっている「温かいお弁当」も、電子レンジ以前にはなく、お弁当は「冷たいもの」が常識だったのです。
●電子レンジの普及と冷凍食品の進化
電子レンジがなければ、冷凍食品はここまで進化していなかったでしょう。
1965年、家庭用電気冷蔵庫の普及率が50%を超える。
1966年、家庭用電子レンジが発売。
冷凍食品を保存するためには、冷凍庫が必要です。まだ電子レンジが家庭に普及していない時代の冷凍食品は、鍋でボイルしたり、 フライパンで焼いたりしていました。冷凍シューマイや冷凍肉まんは、蒸し器を使って温めていたのです。それが電子レンジの普及で、一気に作業が楽になりました。
特に近年では、家庭で作るより美味しいんじゃないか? と思うような冷凍食品も増えてきました。冷凍ピザなんて、生地がサクサク、チーズがとろ〜りなんて当たり前。レンジ温めるだけで、プロ並みの料理が楽しめる時代になったのです。
●電子レンジは手抜きか?
電子レンジの普及によって、「手作り料理」の概念も少しずつ変わってきました。「電子レンジを使って作る料理は手抜き料理」という人もいる反面、むしろ「手軽に美味しく食べられることが正義!」という考え方が広まってきたのです。いまや家庭料理でも電子レンジがないなど考えられません。
電子レンジを活用した簡単レシピも多く、「レンジでパスタ」「レンジで肉じゃが」など、時短&美味しさを両立した料理が次々と生まれています。
また、料理初心者でも「レンジなら失敗しにくい」というメリットがあります。火加減の調整が不要で、時間さえ守れば誰でもそれなりの料理が作れるわけです。まさに、料理のハードルを下げてくれた救世主ともいえるでしょう。
電子レンジは、私たちの食文化を大きく変えました。料理の時間短縮、コンビニの進化、冷凍食品の発展、そして「家庭料理」の価値観まで影響を与えています。
そして、これからも進化は止まりません。いまやAI(人工知能)を搭載し、話しかけるだけで設定ができてしまう電子レンジもあるのです。
もしかすると、未来の電子レンジは「チン」ではなく、「シュッ」とか「ピカッ」とか、新たな音を響かせるかもしれません。これから電子レンジがどんな進化を遂げ、未来の食文化にどんな影響を与えるのか、目が離せませんね。
(巨椋修(おぐらおさむ):食文化研究家)2025-04