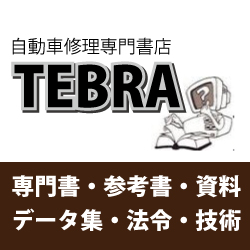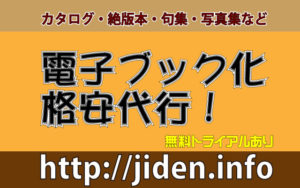(絵:そねたあゆみ)
●食は薬という思想
『医食同源』という言葉があります。この言葉、実は日本で作られた造語なんですよ。元々は『薬食同源』という中国の言葉でした。
『医食同源』という言葉は1972年、NHKの『きょうの料理』という番組で使われたのが最初。『薬食同源』だと、『薬』が化学薬品を連想させるのではという考えから、『医食同源』という言葉にしたのだそうな。
でもまあ意味は同じ。食べ物は薬と一緒ということです。いわゆる『薬膳』ということですね。食べ物は薬と一緒。体にいいものを食べましょうということです。
●健康と食
江戸時代の日本人にとって、肉は薬として食べられていました。タンパク質のほとんどを米と大豆、わずかな魚で摂っていた昔の日本人にとって、肉は滋養強壮の薬同然だったのです。
玉子もそうです。いまの値段だと一個400円ほどもした玉子は贅沢品、病気のときなどに精を付けるために食べていました。玉子には上質のタンパク質にビタミン、ミネラルも入っている完全食なので、下手な健康サプリよりはるかに効果的。現代人でも一日一個は食べたいところです。
江戸では、白米が中心でおかずはほとんどありませんでした。そのためビタミンB1欠乏症である脚気という病気で亡くなる人がたくさんいました。玄米にはビタミンB1が含まれているのですが、精製した白米にはビタミンB1には含まれません。そのため脚気になるのです。江戸の人たちは脚気予防のために好んで蕎麦を食べたといいます。
蕎麦にはビタミンB1がたっぷり含まれていたからです。まだビタミンの存在はわかっていませんでしたが、江戸っ子たちは経験上で知っていたのでしょう。
また、たくあん漬けにもたくさんのビタミンB1が含まれており、これも脚気予防として好んで食べられていたようです。
また、体が冷えたら生姜湯を飲んだり、逆に暑い夏にはキュウリやナスといった体を冷やす効果があると言われているキュウリやナスを食べて、健康に過ごそうとしていたようです。
●歴史上はじめて健康と美容のために食べないという文化が生まれた
ときは流れ、いまや21世紀。21世紀の日本は江戸時代と違って、食べ物があふれている時代。日本は食糧の廃棄率が世界でトップクラスでもあるそうな。
そんな飽食の時代ですから、昔と違っていかに食べないかということに苦労する人も多くなっています。
それは健康のためのフィットネスであったり、美容のためのダイエットであったりするのですが、例えば最近流行している糖質制限ダイエットは、糖質、つまり砂糖や炭水化物をカットすることで、体重や脂肪を減らそうというもの。
砂糖は一昔前なら、なかなか口にできない贅沢品であり、炭水化物はコメやムギといった命を繋ぐための大切な食べもの。これらを食べないようにして痩せよう、健康になろうという人がたくさん出てきました。
おそらく人類史上はじめてのことでしょう。先進国には豊富に食糧があり、それを食べ過ぎないように苦労するという新しい食文化が生まれたのです。
今後いかにカロリーを減らすか、糖質を減らすかといった料理が開発され、それが主流になってくるかも知れません。それも食文化の一面なのでしょう。
(食文化研究家:巨椋修(おぐらおさむ))2019-07