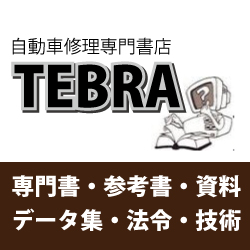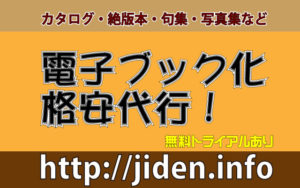古代ギリシアを代表する指導者と言えば、やはり、ペルシア戦争を勝利に導いたアテネの指導者・テミストクレスがあげられるが、一方で、アテネ民主政というものは、テミストクレスにとっても「使い勝手が良い」体制であったということも一面の事実である。
古代ギリシアでは、「戦争の是非」から「配偶者の浮気」まで、様々に神のお告げ、つまり、神託に頼った。(医療技術も未発達な時代、人が神にすがることを嘲笑するのはいささか酷であったろう。もっとも、ギリシア神話の神々は、人も天地も創造していないから、責任を問われることはないのだとか。)ただ、当時の神託は、薬でトランス状態に陥った巫女が意味不明の言葉を口走ったものを神官が人間の言葉に翻訳するというものだったとか。(古代ギリシアでは、50歳以上の女性は神から予知能力を授けられていると考えられていた。当時はそれほどに50歳以上生きる女性が少なかったということなのだろう。今なら100歳以上か。あるいは、自活できない高齢女性の生活保護的な意味合いもあったのかもしれない。青森恐山のイタコにも共通するような気がする。)つまりは、結局、神官の腹一つだったのだろうが、神官も責任は取りたくないから、どうとでもとれるような謎めいた韻文詩という形で伝えた。
一例をあげると、紀元前499年のペルシア戦争時、アテネは「アテネがために木の砦をば、唯一不落の塁となり、汝と汝の子らを救うべく賜るであろう。聖なる神の穀物が蒔かれる時、あるいはその採り入れの時に、そなたは女らの子らを亡ぼすであろう」という神託を得た。なるほど、「ノストラダムスの大予言」ではないが、どうとでも解釈できる内容である。
アテネでは、当初、この「木の砦」を「籠城」と解釈し、籠城に傾きかけたが、テミストクレスは、「木の砦は船を指すものだと解釈できる」と主張。結果、アテネは海軍を増強し、強大なペルシア軍を破ったという。だが、テミストクレスほどの人ならば、「神のお告げ」がバカバカしいものであることはわかっていたはず。しかし、彼は神託を正面から全否定することはせず、自らの考えに合った解釈を打ち出すことで議論をリードした。ただ、それでも、籠城説に拘る連中はいたはずで、おそらく、テミストクレスは「ああ言えばこう言う」式で、諄々と言って聞かせるように論破したのだろう。(確かにこういうときには、「神の意向」は役に立つ。)が、面倒と言えば面倒なやり方だし何より、頓智問答にも似て、抜群の頭の良さと機転が必要とされる伊藤博文のような調整型タイプにはあっていただろうが、ヒトラーには使いこなせなかったような気がする。
(小説家 池田平太郎)2025-06