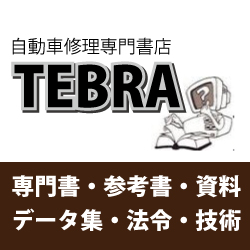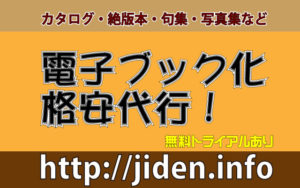(絵:吉田たつちか)
人類が料理をするようになったのは、火を利用するようになってからだと言われています。肉にせよ植物にせよ、食べ物を焼くことによって、柔らかく食べやすくなり消化しやすくなります。ジャガイモで例えると、生のままだと30%しか消化できませんが、加熱すると98%も消化できるようになります。さらに火を通すことで殺菌効果があり、より安全に食べることが可能になりました。ライオンやオオカミといった生肉を食べる動物でも、食中毒になることがあるそうです。人類は火を使うことで、より安全に食料にありつくことができるようになりました。
焼き方は、最初は直火焼き、そしてフライパン代わりに薄い石の下に火を焚いた石焼などであったことでしょう。やがて人類は土器を作ることを覚え、煮る・炊くといった料理ができるようになります。しかし欠点もありました。火を通した肉は、ビタミンやミネラルが減ってしまいます。そのため肉以外の植物などをより多く食べる必要が出てきました。
人類が生肉を食べていたころ、生肉の血液にはナトリウムなど塩分が含まれており、特に塩を摂る必要はありませんでした。しかし火を使い肉を焼くようになると、身体が塩分を求めるようになります。さらに肉に塩をつけて食べると、その美味しいこと美味しいこと。肉に塩を振ることで塩味がつくだけではなく肉の臭みを取ることができます。また、肉の余分な水分を浸透圧で出し、旨味を引き出すことができることを発見します。
さらに人類は塩に保存効果があることを知ります。原始の人類にとって、塩はなくてはならないものになったのです。
やがて人類は農耕をはじめ穀物中心の食生活になると、ますます塩が不可欠になり、塩は調味料の基礎中の基礎になるだけではなく、発酵の調整、傷口の消毒など、生活必需品になりました。
メソポタミア文明やエジプト文明など、古代文明が発祥した地域には、必ず塩の生産地がありました。文明と塩の関係は塩の製法がメソポタミアからエジプト、ギリシア、ローマへと伝わったことからもわかります。
古代ローマ時代、兵士の給料は塩(ソル:sal)であり、英語のsalary(サラリー:給与)はここからきています。塩をもらう人がサラリーマンというわけですね。
ソース(sauce)の語源も塩(sal)。ソーセージ(sausage)の元々の意味は肉の塩漬けという意味のラテン語サルサス(salsus)。サラミ・ソーセージのサラミ(salami)も同様。サラダ(salad)も古代ギリシアや古代ローマで生野菜に塩を振って食べたことから、このような名称になったそうな。
このように人類は、火と塩を利用することで料理というものを作るようになりました。
さて、いよいよ夏になりましたね。夏は汗をかくため、塩分を多くとったほうがいいといいます。一方で塩分の摂りすぎは健康に良くないとも言われます。ここらへんの【塩梅】がとても難しいと思う今日この頃です。(巨椋修:食文化研究家)
(食文化研究家:巨椋修(おぐらおさむ))2022-07